そもそも、ニューオータニの中に美術館があるのなんて、ぜんぜん気付いてなかったわたくし…。
日曜とはいえ午後遅い時間のため、そもそも人が少ない。
最近、展覧会に行くと人がたくさんで、それだけで萎えることが少なからずあるので、これはうれしい。
展示は、17世紀後半から、時代を追って肉筆浮世絵とひなかた、そして小袖(帯も少々)を組み合わせていた。
肉筆浮世絵は、8月に江戸東京博物館でたくさん見たので、それに較べるとちょっと…とか思ってしまった。実は、一番最初に展示してある、サントリー美術館の「舞踊図」屏風が一番よかったかも…(汗)。
とにかく江戸期の小袖をいろいろと見ることができたのがうれしかった。
もちろん、布というのは、経年変化には弱いものなので、作られた当時の色とはだいぶ変化しているのだろうけれど、江戸期の刺繍や絞り、手描き、箔、地紋といった手間をかけた仕事を間近で見ることは、なかなか機会がないのでじっくりと。
そして、一通り展示を見終えた後、振り返ってみたら「ああ、江戸期のこういう小袖っていうのは、単なる衣料品ではなく、美術品でもあったんだなぁ」ということを改めて感じた。
近くで手仕事を見ているときには気付かない、全体の構図や色・柄の取り合わせの大胆さは、現代のきものにはない。
展示から離れて見て、わかることもあるんだなぁ…。
たとえば、寛文期の「黄綸子地雪輪竹模様小袖」。
近くで見ていると雪輪がイマイチよくわからないのだけれど、離れて全体を見ると「なるほど!」と。
公式サイトによると、この時代はすでに桃山期の影響を脱して、江戸独自の最初の流行とのこと。
そして元禄期になると、友禅染が発達し、さらに、帯の幅が広がることによって、上半身と下半身の柄が分かれ、そこからさらに「腰模様」と呼ばれる、腰から下に模様を施すスタイルが流行していく。
それが、江戸の人々の「粋」という美意識によって、「裾模様」と呼ばれるきものの裾の部分のみに模様を施すスタイルが生まれる。
その例として展示されているのが「白綸子地松竹梅模様小袖」。
また、逆に帯の位置に左右されない意匠としての「総模様」が誕生した。これは、現代の「小紋」に通じるデザインかな?
その例が「白縮緬地垣楓模様小袖」。
それにしても、こんな小袖をどんな女性が身にまとっていたのだろう? 一緒に展示されている浮世絵の題材になっているのは、ほとんどが遊女なので、やはり吉原あたりの花魁なのかな?
そして、きもののほとんどが国立歴史民俗博物館の所蔵品。やはり、一度、折りを見て、佐倉まで行くべき???
こじんまりとした会場なので、点数は多くないけれど、なかなかステキな展覧会だった。
特に、きもの好きな方には、オススメ。
10月25日までが前期で、10月27日から展示替えが行われて、違う作品も見られるとのことなので、後期も見にいきたいな、と思う。
※上記で名前をあげたきものの画像は、「肉筆浮世絵と江戸のファッション 町人女性の美意識」で見られるので、ご参照ください。
<参考になりそうな本>

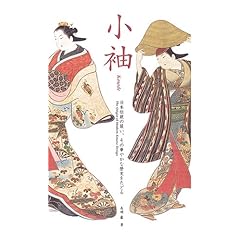





0 件のコメント:
コメントを投稿