その「石川五右衛門」の原案を書いた、樹林伸さんによる、歌舞伎入門書が、8月下旬に上梓されたので、さっそく購入して読んでみた。
樹林伸『「でっけぇ歌舞伎」入門 マンガの目で見た市川海老蔵』
(講談社+α新書)
「はじめに」で、樹林さんは
十一代目市川海老蔵という役者に出会うことによって、僕自身、大きく変わりました。と書いている。
たとえば、歌舞伎にたいする考え方です。
歌舞伎をまったく知らなかった僕は、歌舞伎をすごく限定的なエンターテインメントだと考えていました。
(中略)
でもじっさいにはぜんぜんちがっていた。歌舞伎という芸能はまだ生きているし、成長を続けている。市川海老蔵は新しいチャレンジをしようとしているし、そのチャレンジによって四百年という長い歴史に、新たな一ページを刻もうとしている。
これは僕にとって大いなる発見であったし、「出会い」がもたらした大きな変化でもありました。
P.3-4
タイトルの「でっけぇ」は、歌舞伎十八番「暫」の中で、主人公の鎌倉権五郎に向かって劇中でかけられる、褒め言葉だ。
実際、この芝居を見たことのある人なら、その実際以上の舞台上での存在感の”大きさ”を褒め称える言葉であることは、わかるだろう。
扮装だけではなく、権五郎を演じる役者の、気持ちの大きさが、観客の目に反映される。どんな役でもそういう面はあるが、特にこの役にはそういう”大きさ”が要求されるように思う。
そして、ここ数年の海老蔵さんの権五郎は、まさに「でっけぇ」にふさわしい。
市川海老蔵という役者は、世阿弥のいう「時分の花」にぴったりだと、ここ2年ぐらいの彼の舞台を見ていて、感じている。
四百年、十二代を数える名門・市川團十郎家を継ぐべき星の下に生まれた彼は、子供の頃からずっと、その重責を担うための英才教育を受けてきた。それでも、團十郎という名前の重圧に押しつぶされそうになったことは、一度や二度ではなかったに違いない。
歌舞伎の家に生まれたということは、まさにそういうことなのだ。
樹林さんも、そのことについて、第三章「シロウトに歌舞伎は演じられるか?」の中で次のように述べている。
「團十郎」は世襲で伝えられているわけですが、待っていれば転がり込んでくるものではない。役者としての充実はむろんのこと、それにふさわしい精神性を要求する「名」なのです。さらに、修行については、こんなことを。
P.81
マンガ原作者として、また、小説家としてたくさんの仕事を抱え、締め切りに追われる樹林さんを、それまでほとんど触れてこなかった歌舞伎の原案作りという新しい仕事に誘い込んだのは、初対面の海老蔵さんが、金丸座の楽屋で発した次の言葉だったという。
歌舞伎役者は小さなころから、歌舞伎を演じるためだけに、長い年月をかけて営々と素地をつくります。言葉は悪いけれども、洗脳に近い教育を受けるわけです。そんな驚くべき修行を積んだ人間だけが、歌舞伎役者になる。
(中略)
伝統芸能の世襲は、重荷のリレーだ、と僕は思います。
受け継ぐものは、何百年もかけて培われてきた「芸」であり、「名」です。「財産」や「地位」ではない。たやすく受け止められるものではなく、子どものころからわけもわからず「芸」を叩き込まれ、バトンを受け取る準備を営々と行ってきた人間だけが、「名」を引き継ぐことを許される。
P.84-85
そして、素人にできるのは「まねごと」だけであり、
歌舞伎の本質は、そういった「かたち」の中にはないのです。小さなころから叩き込まれ、磨き上げられた役者の素地と精神性。その中にこそある。
P.87
彼はあの射るような眼で僕を見つめながら、こんなことを言いました。
「樹林さん、歌舞伎って、いろんな縛りがあって、できないことだらけだと思ってませんか」
(中略)
「そんなことないんです。歌舞伎は、しようと思えばどんなことでも表現できるんです。できないことはなにもないと思って、ストーリーを考えてみてくれませんか」
(中略)
「歌舞伎だと思って書く必要はありません。ふだん樹林さんが書かれている、マンガのシナリオだと思って書いてください。残念ながら、今、歌舞伎の現場には、おもしろいストーリをつくれる人がいない。そういう人材は、マンガやアニメ、ゲームなどの、今いちばん勢いのあるエンターテイメントの現場にいるんだと思っています。僕はそういう人と仕事がしてみたいんです」
P.36-37
海老蔵さんは、「石川五右衛門」の製作発表の席で「新作の古典をやりたかった」と話した。歌舞伎の文法を使いながら、現代の人に共感してもらえる新しい作品をやりたかった、ということだ。
舞台を見ていて、竹本(歌舞伎の際に演奏される義太夫節)や、下座音楽(舞台下手の御簾の中などで演奏される三味線・唄・鳴り物による音楽)、附け、といったモノが上手に取り入れられていて、その中にも「へぇ~」と思わされるような演出が施されていて、「あ、これは歌舞伎だ」と素直に思うことができた。
新作歌舞伎というと、突飛な演出や舞台装置、効果音、洋楽などを取り入れがちだけれど、そういうものは、やはりどこかで浮いて見えてくる。歌舞伎役者の身体技能に馴染まないからであろう。
そういう点があまり見受けられなかったのは、海老蔵さんとスタッフの間に共通の認識がしっかりと出来上がっていたからだろう。
あとがきのかわりに、海老蔵さんと樹林さんの対談が収録されている。
この対談が、かなり砕けた話まで収録されていて、その点もかえって好ましく感じられた。
そんな中で、特に印象に残っている海老蔵さんの言葉を引用しておくと
歌舞伎って本来、新作をやるものだったんですよ。江戸時代には毎年毎年、新しい演目が演じられていたんです。でも、今はそうじゃなくなってますよね。古い演目を繰り返し演じるものになってしまっている。もちろん、古いものを大事にすることも大切なんだけど、それだけじゃダメなんじゃないか、と思っていたんですよ。新しいことをやっていかなきゃいけないんじゃないかと。
P.162
結局、「石川五右衛門」も、『「でっけぇ歌舞伎」入門』も、樹林伸から市川海老蔵に宛てた、ラブレターなんじゃないかな?
海老蔵さんについては、こんな本も出ているので、参考まで。
『写真集市川海老蔵 (十一代目襲名記念)』
村松友視『そして、海老蔵』(世界文化社)


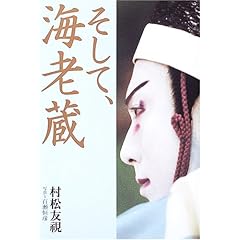




0 件のコメント:
コメントを投稿