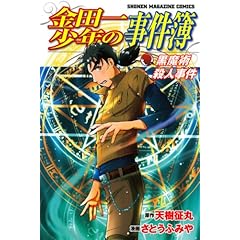
まだまだ、工夫の余地はあると感じたけど、海老蔵さん、石川五右衛門というチョイスは正解。
今月の演舞場は、樹林伸さん原案の「石川五右衛門」。
樹林伸さんって???と思ったら、「金田一少年の事件簿」や「神の雫」の著者とのこと。
どちらも、読んだ事はないが、タイトルぐらいは知ってるぞ、わたしだって(笑)。
海老蔵さんが、樹林さんにオファーした、ということを筋書で読んだ。
「金田一少年の事件簿黒魔術殺人事件」(少年マガジンコミックス)
※樹林さんも出席した製作発表会見の模様は「歌舞伎美人」サイトで読める。
ちなみに、Amazonに樹林伸さんの近著が掲載されていました。ちょっと楽しみ。
「でっけえ歌舞伎」入門 マンガの目で見た市川海老 蔵」(新書)
石川五右衛門は、五代目と七代目團十郎が演じて好評を博した演目ということで、市川家にはゆかりの深い演目とのこと。
※「歌舞伎美人」サイトの「みどころ」参照
五右衛門といえば、「楼門五三桐」の「絶景かな、絶景かな」というセリフでおなじみの芝居が思い浮かぶ。南禅寺の山門の上で、煙管を手に、厚手のビロードの着付けに百日鬘で腰掛けている五右衛門が大セリで道具のセリ上がりとともに現れるところは、絢爛豪華な装置も見物の場面。
今回の新作は、こうした古典の筋を踏襲しつつ、新たな場面も加え、かつ、歌舞伎らしい下座音楽や演出が用いられているという意味で、「新しい古典」になり得る要素は十分に備えている。
ただし、このままでいいかというと、まだまだ、刈り込み・書き足し・工夫は必要だと思うが。
発端。五右衛門の釜茹でのシーンを義太夫にのせた人形振りで演じられる。木村常陸介は、ちょうど「阿古屋の琴責め」で出てくる岩永左衛門を思わせる赤面で、眉毛が人形のように動くところなど、ユーモアがあって、短いながらも客を歌舞伎の世界に引き込むには、よい仕掛けだと思う。
序幕。釜茹での場面から一転、伊賀山中に場所が移る。祠の前に倒れていた五右衛門を見つけた百地三太夫が、一番弟子・霧隠才蔵に命じて、伊賀忍の術を教える。その様子を、立ち回りを交えて見せていく。演出の工夫が、もうちょっと欲しいところ。ただし、ここの場の附けがうるさい! 囃子がまったく聴こえないほど大きな音で打つのは、かえって邪魔になる。ここは附け打ちさんと役者・囃子方で話し合って調整していただきたいところ。
二幕目。場面はまた変わって、聚楽第の奥庭。秀吉の愛妾・茶々と五右衛門の出会いと二人の初恋の模様を、長唄+筝曲の地に乗せた所作事で見せる。茶々は七之助くん。ここの長唄がねぇ…だからなのか、そもそもなのか、ちょっと判断は保留するが、この場は長い気がした。まぁ、演出が藤間宗家だから、所作事が長くなるのも、わからないでもないのだけれど。
もうちょっとコンパクトにまとめると、良いと思う。
三幕目聚楽第お茶々の寝所の場。逢瀬を重ねた五右衛門と茶々だけれど、いつまでも続く訳もなく、五右衛門が茶々に別れを告げる。気分がすぐれないと、自室に引きこもっている茶々を、前田利家が訪ねてくる。この時、利家が全身真っ赤な裃姿なのかが、謎だ…。
茶々の身を案ずる利家に、妊娠したことを打ち明ける茶々。そこへ、團十郎・秀吉がいよいよ登場。茶々の懐妊を知り、喜ぶ秀吉だが…。
この場は、そもそも利家がなぜたずねてきたのかが、イマイチ説明不足だなぁ。五右衛門との密会に気づいてやってきたのか、本当に彼女の身を案じてきたのか、利家が退場してもその辺のあいまいさが、引っかかる。
南禅寺山門内陣の場で、五右衛門に呼び出された秀吉が、秘密を打ち明ける。ここは、照明が暗くて、たいした道具も飾られていないし、、二人だけのやり取りで進行していくしで、もうちょっとテンポをよくしないと、肝心な場面なのに、飽きる…。
そして南禅寺山門の場。ここが、「楼門五三桐」の「山門」にあたる場面かと思ったら、まだクライマックスはこの後にとってあるので、さほど派手さはなし。
大詰。大阪城天守閣大屋根の場。大薩摩でつなぐのは、お約束。こういうところをきっちり作るのは、さすが宗家。だけど、大薩摩がねぇ…。
ここで、五右衛門は、伊賀忍びの術を繰り出して、派手な立ち回りを見せる。分身の術の見せ方なんかは、ある意味原始的なのだけれど「おお、この手があったか!」という演出の工夫があって、楽しい。
三条河原釜煎りの場。大きな釜がしつらえられた舞台面は、発端と同じ。ただし、その釜を取り囲む人数は、増えている。そして、いよいよ五右衛門が釜の中に飛び込むと、中から葛篭が浮かび上がり、舞台の上をふわふわと飛ぶ。そして、その葛篭が消えると、花道スッポンから一回り大きな葛篭が吊り上げられ、葛篭が割れると中から海老蔵・五右衛門の登場。釜の中に葛篭が仕込まれていたのは、あの人の情け、というセリフで「なるほど、五右衛門の葛篭抜けってのは、そういうことだったのか!」と納得。
海老蔵さんが葛篭を背負って、空中六法をすると、柄の大きさと手足の先まで、神経の行き届いた動きで、力強さの中に美しさがあって、まさに「花形役者」だなぁと。この釜煎りの場を見るだけでも、かなり満足感はあった。
個々の場面について、注文はいろいろあるのだけれど、見落としている部分もあるかと思うので、全体を通して感じたことを。
まず、義太夫狂言でありながら、義太夫が面白くない。言葉が伝わってこないのは、問題。再演があるならば、人選含めて、工夫をしていただきたいところ。
人がいない、とはいえ、もうちょっと人間模様を厚めに描いて欲しい。せっかく市蔵さん、猿弥さん、右近さんがいながら、しどころがあれしかないのは、もったいない。これも、再演の折には、もうちょっと工夫をしていただきたい。
とはいえ、新しい原案を歌舞伎古来の手法で、それぞれのいいところを活かしたという意味では、新作歌舞伎の一つの方向を提示した作品だと思う。
これを、1回限りの上演で終わらせるのではなく、さらに手を加えて、「平成の歌舞伎」として、後世に伝わる作品に育てていって欲しいと願う。




0 件のコメント:
コメントを投稿